小学校の役員とは?どんな仕事があるの?
小学校の役員といえば、多くの保護者が関わるPTA活動が中心です。しかし、具体的にどのような仕事があるのか不安に思う人も多いでしょう。ここでは、小学校の役員の主な仕事内容や選出方法について解説します。
役員の主な仕事内容と役割は?
小学校の役員には、以下のような役割があります。
- PTA会長・副会長:PTA全体の運営を担当。
- 書記・会計:会議の議事録作成や資金管理。
- 広報委員:学校行事の広報やPTA会報の作成。
- 学年委員:各学年の行事運営のサポート。
- ベルマーク委員:ベルマークの集計・送付。
- 地域安全委員:登下校の見守り活動。
役員の選び方や決まり方は?
役員は、主に以下の方法で決まります。
- 立候補:自発的に引き受ける。
- 推薦:他の保護者や先生の推薦。
- くじ引き:立候補者が少ない場合に実施。
このため、「役員をやらずに済む方法」を模索する人もいますが、学校によっては一定期間で全員が経験するような仕組みになっていることもあります。
低学年のうちに役員をやるべき?メリット・デメリット
役員は「早めに済ませるべき」という意見もあれば、「高学年になってからのほうが楽」という声もあります。ここでは、低学年で役員を引き受けるメリット・デメリットを整理します。
低学年で役員をするメリットは?
- 比較的負担が軽い
- 高学年よりも行事の数が少ないため、業務量が抑えられる。
- 先生や他の保護者と顔見知りになれる
- 早い段階でコミュニティを作れるため、後々の情報交換がスムーズに。
- 後が楽になる
- 高学年での役員は負担が大きくなるため、低学年で済ませることで回避可能。
低学年で役員をするデメリットは?
- 学校のルールや行事に慣れていない
- 入学したばかりだと、学校の仕組みを理解するのが大変。
- 下の子がいる場合は負担が大きい
- 乳幼児がいる家庭では、役員業務との両立が難しいことも。
- 仕事との両立が厳しいケースも
- フルタイム勤務の人にとっては、低学年の時期に役員をするのが難しい場合も。
役員経験者のリアルな体験談!
低学年でやってよかった人の声
「1年生の時に役員を引き受けました。負担が少なく、先生や他の保護者とのつながりができたのが良かったです。おかげで学校生活の情報が入りやすくなりました!」(40代・会社員)
低学年でやって後悔した人の声
「下の子がまだ2歳の時に役員を引き受けましたが、会議に出席するのが大変でした。幼稚園のお迎えと重なることも多く、もっと余裕ができてからのほうが良かったかも…」(30代・専業主婦)
忙しくても役員を乗り切るコツとは?
- 負担が少ない役職を選ぶ
- 他の保護者と協力しながら進める
- スケジュール管理を徹底する
- 家族と事前に相談しておく
小学校役員のおすすめアイテム・サービス
- Googleカレンダー(スケジュール管理)
- LINEグループ(情報共有)
- クラウドストレージ(Google Drive)(資料整理)
- オンライン会議ツール(Zoom・Google Meet)(会議の負担軽減)
小学校の役員に関するよくある質問(FAQ)
役員をやらないとどうなるの?
役員は強制ではない学校もありますが、「次年度以降、優先的に選ばれる」などのペナルティがある場合もあります。
仕事をしている人でも役員はできる?
フルタイム勤務でもできる役職があるので、事前に学校側に相談するのがベストです。
役員の負担を減らす方法はある?
オンライン会議の活用や、他の保護者と役割を分担することで負担を軽減できます。
低学年で役員をやるならどの役職がオススメ?
比較的負担が少ない「ベルマーク委員」「広報委員」がオススメです。
まとめ|小学校の役員は低学年でやるのが正解?
「いつやるのがベストか」は家庭の状況によりますが、負担を軽くするなら低学年のうちに終わらせるのも一つの方法です。役員を引き受ける際は、自分の状況を考慮し、無理のない範囲で関わるようにしましょう!

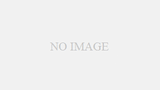
コメント