先生はなぜ「お気に入りの子」を作ってしまうのか?
教師も人間です。教員の多忙な日常の中では、素直に反応してくれる子や、指示をよく聞いて行動できる子に対して自然と親しみを感じやすくなります。それは意図的な「ひいき」ではなく、無意識な好意であることも多いです。特に成績が良い、明るい、礼儀正しいなどの特徴を持つ子どもは、良い印象を持たれやすい傾向があります。
子どもが「差別されている」と感じる時のサインとは
子どもは非常に繊細です。先生が誰かを贔屓していると感じたとき、以下のようなサインを見せることがあります。
- 「○○先生は、△△ちゃんばっかり褒める」と話す。
- 学校での発言回数や発表の機会が少ないと感じている。
- 登校を渋るようになる。
保護者としては、こうした言葉や態度を見逃さず、しっかりと子どもの気持ちを聞く姿勢が大切です。
保護者が冷静にとるべき3つの対応ステップ
子どもの話を丁寧に聞いて状況を整理
まずは感情的にならず、子どもの感じていることをじっくり聞くことが第一歩です。事実と感情を分けて受け取り、必要があれば他の保護者やお子さんにも話を聞いて客観性を補いましょう。
教師に直接ではなく、学校内の別の窓口へ相談
担任に直接抗議すると対立関係になりやすいため、まずは学年主任やスクールカウンセラーといった中立的立場の人に相談するのが賢明です。第三者的視点で状況を把握し、学校側も対応しやすくなります。
最終的な判断は「子どもの成長」に基づく
相談をしても改善が見られない、あるいは子どもの心身に影響が出ている場合は、環境を変える決断も選択肢の一つです。学区変更や転校、通信教育なども柔軟に検討することが大切です。
「お気に入り行動」が与える子どもへの心理的影響
不公平に感じる扱いは、子どもの自己肯定感を下げる要因になり得ます。 また、「お気に入り」とされる子自身も、周囲からの嫉妬や孤立感を抱えることがあるため、決して一方的に「得している」とは限りません。
健全な学級環境を育むために家庭ができること
家庭では「あなたの存在は大切」と伝えるコミュニケーションが重要です。学校で嫌なことがあっても、家庭では安心して話せる環境をつくることが、子どものストレス軽減につながります。 また、先生にすぐ抗議するのではなく、子どもの成長を最優先に考えて対応する姿勢を持つことが大切です。
まとめ:感情ではなく冷静な行動が、子どもを守る
先生の「お気に入り行動」は、必ずしも悪意によるものではないこともあります。 子どもが感じている違和感を尊重しつつ、保護者としてできる行動を冷静にとることが、子どもの健やかな成長を守る最善の方法です。

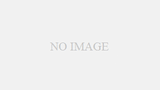
コメント